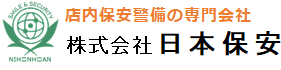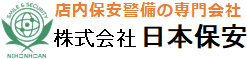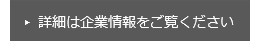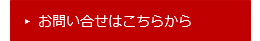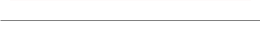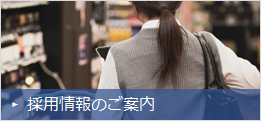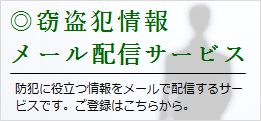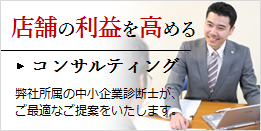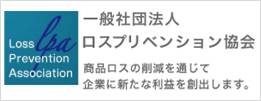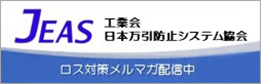第4話:「削減して良い経費」と「削減してはいけない経費」を考える
■STEP2:最大の害は商品ロス 2017/04/13
前回は経費管理の計画と早期判断のついてお伝えしました。
ポイントは以下の3つです。
「①分類を小さく」、「②単位を細かく」、「③判断を早く」の3つです。しっかりと管理をして利益性を高めていきたいですね。
さて、一方で経費を管理ではなく削減する必要に迫られている企業も近年多くなっているのではないでしょうか?
小売業にとって規制緩和は諸刃の剣でしょう。営業時間の延伸、競合店の増加など様々な影響をもたらし、既存店は商圏が狭まり、老朽化とともにジリジリと収益性を下げていきます。そんな中、一定利益を確保する必要にかられた企業は経費を管理ではなく、削減しなければならいケースに直面します。
初めは、重要度も緊急度も低いと思われるものから、徐々に重要度が高くても緊急性の低い経費が先送りされていきます。一度先送りが始めるとなかなか元のペースに戻すのが難しくなります。
こういった状況の中、時折誤った過った経費削減をしてしまっている店舗を見かける事があります。小売業にとっての生命線はお客様満足であり、リピートです。どれだけ多くのお客様にまた来ていただくかが勝負です。しかし経費削減圧力に押され、お客様のお買い物にとって悪影響を与える選択をしてしまうお店も存在しています。
たとえば水道光熱費を削減したいがあまり、売場の照度を落としてしまう、もっとひどいときは蛍光灯を抜いてしまうお店も見受けられます。ただでさえ業績が厳しいから、経費削減がせまられているのに、そんな事をしてはお客様の心地よいお買い物をできなくなり、ますますお店から心が離れます。結果的に業績は更に悪化します。するとさらに経費を削減しなければなりません。結果バッドスパイラルへと入り込み、症状はどんどん悪化し、立て直しも厳しくなっていきます。
お客様への商品・サービスの提供に影響がない費用は削減しても、影響があるものについて手をだすと、その後に甚大なマイナス影響が発生してしまいます。
では削減してもよい費用にはどんなものがあるのでしょうか?その筆頭に上がるのが、STEP2のタイトルである「商品ロス」です。
棚卸の際に季節物のように話題になりますが、継続的な取り組みがなされていないケースが多々あります。多くの費用は何らかの効果を得るために支払いますが、商品ロスは同じ費用項目でも損害です。一部の業種以外では注目度の低い商品ロスは、百害あって一利なしの何の役にも立たない費用です。
小売業にとって削減しても良い費用であるばかりが、存在そのものが悪であるにも関わらず意外と注目度が低いのが現実です。次回はこの商品ロスについて詳しくお伝えしてまいります。
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
【 筆者プロフィール 】
株式会社 せんだ兄弟社 代表取締役 専田 政樹 (https://kyodaisha.com)
株式会社 日本保安 店舗支援PJ担当シニアコンサルタント
7&iグループ出身、小売業歴20年の中小企業診断士
店舗運営管理、販売スタッフ教育等を経験後、グループ内事業会社へ転籍し、小売業から製造小売業への転換を目指す新商品開発部門でSV、VMD、マーケティング、プロモーション企画等を担当し、外部専門職のマネジメント業務等に従事。その後、管理部門の責任者を務め、営業利益▲3%から、1年で+0.5%に改善した実績を持つ。
「次代を担う子供たちに【明るい未来】と【豊かな社会】を託す」事を志に独立開業。2017年3月、企業の人に関する支援を行う㈱せんだ兄弟社を設立。組織人事、各種制度構築、業務改善、人材育成などを事業領域として活動中。
→プロフィール詳細